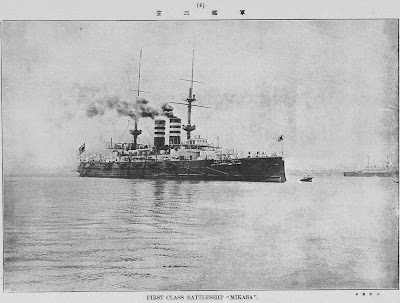東郷長官の心算
回顧すれば、二十九年前の昨日から今日に掛けて戦はれたる日本海々戦は、真に我が日本の国運を賭けての一大決戦であつて、聯合艦隊の将兵は全く必死の覚悟を以て奮戦いたしたのであり、当時を追想すれば
洵に血湧き肉躍るの思ひが致すのであります。実際「皇国の興廃此の一戦に在り」で、艦隊司令長官としての東郷さんに於かれては、固より深く心に期する所があり、随分と思ひ切つた必勝的決戦を企図せられたのであります。時も時、東郷老元帥の重態が伝へられまして、吾々国民として邦家の為に誠に痛心の至りに堪へません。何卒一日も早く元帥の御本復に相成る様皆様と共に衷心より御祈りする次第であります。――(満堂粛然)
さて、その東郷さんの計画と申すのは、五島列島の沖から
浦塩の沖に掛けて六百
浬に亘る海面を、所謂七段備への戦法で、四日三晩ぶつ通しで敵に息をもつかせず、昼戦夜戦と連続交互に戦ひぬいて、一艦一艇も餘さず、敵の艦隊を全滅してしまはうと云ふのが、東郷長官の心算であり計画であつたのであります。
扨て愈々敵と相
見えての実戦舞台となりますると、之は又お膳立に一段と
縒を掛けての猛烈さで、全く眼の覚めるやうな合戦ぶり、水も漏らさぬ七段構への戦法は悉く壺に嵌まつて、
而かも第三段、第四段、第五段の三段だけで見事に所期の目的を達成したのであります。即ち戦さは第三段から始まつたのであつて、其の第三段である対馬沖の昼戦は廿七日の午後二時を以て開始せられ、激戦実に五時間餘に亘り、さしも頑強の敵艦隊を散々に撃破して、敵の旗艦スワロフを初め七隻を撃沈し、日の
将に西に没せんとする午後七時半、敵の戦艦ボロヂノが我が砲弾の為に爆沈したのを最後として戦場を夜戦部隊に譲り、戦闘艦と巡洋艦の各戦隊は茲に其の合戦を切上げ、何れも翌朝の豫定戦場たる
鬱陵島の南方に向つて急いだのであります。
そこで戦さは第四段の夜の戦に移り、我が駆逐隊及水雷艇隊四十餘隻は北方、東方、南方より三面包囲の姿勢を以て、所謂意気衝天の勢で飽く迄敵に肉薄し、昼の戦ひに
傷いて疲労困憊せる敵艦隊を縦横無尽に駈け悩まし、遂に其の四隻を撃沈したのであります。
明くれば第五段の鬱陵島南方二十八日の昼戦である。即ち二十九年前の今日、これは又前日と違つて誠に天気の好い、追撃には以て来いの展望百パーセントの戦さ日和で、日本海の
此処彼処には忽ち劇烈なる総追撃戦が開始せられた。戦場の
広袤実に二百浬に亘り、大小の合戦無慮八場面に及んだのでありますが、中に就いてその最も目覚しかつたのは、我が主力艦以下各戦隊の二十八隻が八方よりネボカドフ艦隊を包囲し、遂に之を降伏せしめた壮絶無比の第四合戦と、敵の司令長官ロジェストウエンスキー中将が旗艦スウオーロフの沈没前に駆逐艦ベドウイに移乗し、浦塩目指して逃走を急ぎつゝあるとも知らず、我が駆逐艦漣が之を発見追撃して遂にロジェストウエンスキー長官
諸共其の駆逐艦を捕獲した、いとも花々しい第九合戦とであつて、絶大の収獲を以て此の海戦の幕を閉ぢたのであります。――(拍手)
東郷長官の深慮
丁度このネボカドフ艦隊降伏の場面に、三笠の艦橋では一つの記憶すべき……歴史劇的の
一と幕が演ぜられたのであります。当日は、三笠では七千メートルから戦闘を開始したのであるが、戦闘を開始して未だ
幾何も経たぬ午前十時四十五分頃であつたが、秋山中佐参謀は敵の艦隊の
檣頭に翻つた「我れ降伏す」と云ふ万国信号を逸早く認めて、東郷さんに向つて
『長官! 敵は降伏しました。我が艦隊の砲火を中止いたしませうか?』
と伺つたが、東郷さんは例の通り左手に
確かと長剣の柄を握り締め、右手に持つた双眼鏡を胸の辺に置き、ジッと敵方を見詰めたまゝ、黙然として一向許さうともされない。秋山参謀は艦橋の甲板を地団太踏まん
許りに声も鋭く、
『長官! 武士の情であります。発砲をやめて下さい。』
と息をはづませて詰め寄つて居るが、東郷さんは愈々冷然として
『本当に降伏するとなら、その艦の進行を止めんけりやならん、現に敵はまだ前進して居るではないか』
と言つて頑として聴き容れられない。これには流石の秋山参謀も一言もなかつた。実際、敵の艦隊は微速力ながら行進を続けて居るのみならず、その艦隊幾十門の大砲はズラッと並んで、発砲こそしないが其の砲口は何れも日本艦隊の方に向いてる。或は我が艦隊に近づいて不意に魚雷攻撃を加へないとも限らない。殊に軽巡洋艦のイズムルードは独り列を離れて脱兎の如く前方に抜け懸けして居る。その行動は魚雷発射に対し頗る疑ふべきものがあるので、我が艦隊は一時之を避けて非敵側の方向に舵を取つた程であつて此の場合東郷さんが軽々しく戦闘中止を許されなかつたのも実は尤もの次第であつたのである。あとから分つたことであるが、降伏したネボカドフ司令官の日誌の一節にも、
『露国の艦隊が降伏の信号を掲げたけれども日本の艦隊は毫も発砲を中止しない。そこで降伏信号のほかに更に日本の国旗を檣頭に掲げ且つ機関を停止せしめたところ初めて日本艦隊の発砲が止まつた』
と記して居るのである。
 |
明治38年5月28日、兵員が整列し日本軍艦旗を掲揚した「アリヨール」号
『日露戰役海軍寫眞帖』第三巻(市岡太次郎等、明治38年、小川一眞出版部) |
斯くて東郷さんは、敵の艦隊が愈々停止し、四囲の状況其の降伏が確実となつたので、初めて全軍に戦闘中止を命令せられ、折よく附近に来合せて居つた雉と云ふ水雷艇を呼んで、秋山参謀を敵の旗艦ニコライ一世に差遣し、ネボカドフ司令官と会見せしめ之を三笠に招致し、茲に降伏が成立したのであります。白髪白髯のネボカドフ司令官が、頭に負傷して繃帯した将校も混つて居る六七人の幕僚を伴つて、三笠の外舷を綱梯子から悄然として這ひ登つて来る其の光景には、実際何とも言ひ知れぬ感慨に打たるゝのであつて、如何に戦ひに気の張つて居る我々も覚えず面を蔽ひ眼にはおのづから血涙が滲み出るのであつた。
扨ても戦さは勝つか死ぬるか二つの外ないことが、切実に痛感されるではありませんか。
 |
「朝日」に収容された「アリヨール」号の副長以下将校
『日露戰役海軍寫眞帖』第三巻(市岡太次郎等、明治38年、小川一眞出版部)
|
何に致せ、前日来の戦闘は確実に我が艦隊の大勝に帰し、今や其の最後の
一と幕を結ばんとして堂々たる我が艦隊廿八隻を以て敗残の小敵ネボカドフ艦隊五隻を包囲して居ると云ふ実況で、実は鎧袖一触と云ふところであつた。
此の場面に処して東郷さんが事を
苟もせぬその慎密周到さ加減は全く別物であつて、之が前日大挙突進して来る敵全艦隊の直前に於て、彼の大角度の正面変換を断行した大胆不敵の司令長官と同一人であらうとは、どうしても思はれない位、此処が即ち、大敵と見て
懼れず小敵と見て侮らず、愈々勝つて愈々兜の緒を締め、折角の此の
九仭の功を
一簣に
虧いてはと云ふ、流石に東郷さんの細心深慮の存する所が見られるのであります。一方に於てはまた智謀神の如き秋山参謀が殺気漲る合戦場裡に示した血あり涙ある大和武士の真に優しき情の一面が窺はれるのであつて、両雄の面目躍如として今も尚ほ眼前に彷彿たるものがあるのであります。
安保清種『東郷元帥と日本海海戰』(昭和9年、軍人會館事業部)より